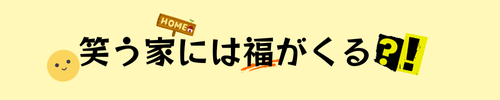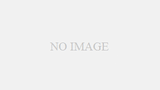はじめに
子連れ離婚を考えるとき、まず大きなテーマになるのが「親権」です。
特に小さなお子さんがいる場合は、親にとっても子どもにとっても大きな分岐点になります。
私の体験:親権はすぐに決まった
まずは、私自身の経験をお話しします。
私が離婚する際は「単独親権」しか選択肢がなく、親権については元夫ともめることはありませんでした。
離婚の話し合いを始めたときから「子どもたちの生活の中心は母親である私」また「元夫が育てるのは子どもにとっていい環境ではない」という認識が一致していたからです。
ただ、子どもの気持ちを優先したかったので、子どもたちに離婚すると伝えたときには「どちらと暮らしたいか」を本人たちに確認しました。その際、離婚しても離れて暮らす方と会えなくなるわけではないし、いつでも会える状況だということも伝えました。
正直、子どもにとって酷な質問だったと思います。けれど私は「親の事情で子どもの気持ちを無視したくない」と考え、あえて希望を聞きました。
結果的に「母親と一緒に暮らす」という答えが返ってきて、私が親権を持つことになりました。
離婚後の名字はどうする?子どもと一緒に考えた選択
離婚後、子どもの名字をどうするかも大切なポイントです。
私は子どもたちに「旧姓」か「現名字」のどちらがいいかを確認しました。子どもが希望したのは「今まで通りの名字でいたい」「名前がかわるのはイヤだ」ということでした。
今時、離婚は珍しくないけれど、名字が変わるということは「離婚したこと」が周囲にすぐにわかります。親しい人達以外にもバレるのは正直、抵抗がありました。子ども達が好奇の目で見られ、そのことで不安定になるのではないかと不安もあったので「現名字」を選択してくれて安心しました。
親権とは?2つの役割(身上監護権と財産管理権)
ここからは法律上の親権について整理します。
親権とは、子どもの成長をサポートし、幸せな人生を歩ませるための、親としての「権利」であり「義務」です。具体的には、以下の2つに分かれます。
- 身上監護権(子どものお世話): 子どもと一緒に暮らして、身の回りの世話、教育、しつけなどを行う権利と義務です。
- 財産管理権(お金の管理): 子どもの財産を管理したり、子どものために契約を結んだりする権利と義務です。
日本の法律では、これまで離婚後は父母のどちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」しか認められていませんでした。
けれど海外では「共同親権」が当たり前で、離婚しても子どもを一緒に育てていくのが普通です。
離婚後の親権、これまでの常識と新しい選択肢「共同親権」
2026年から選べる「共同親権」とは?
2024年の民法改正により、2026年から離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選べるようになります。
これは、子どもが離婚後も両方の親と継続的に関わることで、精神的に安定し、健全な成長を促せるという考えに基づいています。
ただし、共同親権はすべてのケースで最善とは限りません。DVや児童虐待があった場合など、子どもの安全が脅かされる可能性がある場合には、単独親権が選択されます。
👉 なお、2025年までは単独親権しか選べません。
親権と戸籍の手続き
親権が決まると、戸籍の手続きも必要になります。
離婚届を出せば戸籍も自動で変わると思われがちですが、実際には別途手続きが必要です。「旧姓」か「現名字」かで手続き内容も変わってくるので注意が必要です。
そのため、私は離婚後も元夫の姓を使い続ける「婚氏続称」という手続きを選びました。(婚氏続称とは、離婚後も元配偶者の姓をそのまま使い続けられる制度です。)
注意点として、離婚後に「婚氏続称」を選んだ場合、再婚してさらに離婚したときに、出生時の姓には自動で戻れません。どうしても戻したい場合は家庭裁判所に申し立てる必要があります。生活上の必要性などが認められれば許可されますが、必ず認められるわけではないため、選択は慎重に考えましょう。
このあたりは役所によって必要書類や手続きの流れが少し違うので、事前に確認しておくと安心です。私は戸籍の移動や名字の選択など、思った以上に作業が多く、時間も日にちもかかったので少し大変でした。
まとめ
親権は「法律上の決まり事」ですが、同時に「子どもの人生に直結する大切な選択」です。離婚は、決して子育ての終わりではありません。形は変わっても、親であることに変わりはないのです。
私のようにスムーズに決まるケースもあれば、親権でもめて長引くケースもあります。今回の法改正によって「共同親権」を選択することで離婚がスムーズにできる家庭が増えるかもしれません。けれど、親権について夫婦でじっくりと話し合うことの重要性は、これまで以上に高まっています。
体験から言えるのは、「子どもの気持ちをどう尊重するか」が後悔しない選択につながるということです。
👉 あなたなら、子どもの気持ちをどう尊重して親権を決めますか? ぜひ一度、ご自身やお子さんの立場に置き換えて考えてみてください。