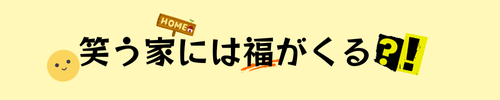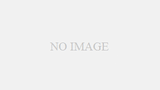はじめに
離婚後の生活を考えたとき、まず頭に浮かぶのが「どこに住むか」ということではないでしょうか。
子どもの生活環境を大きく変えることなく、安心して暮らせる場所を確保したい。でも、何から手をつければいいか分からない…そんな不安を抱えている方も多いでしょう。
私自身、離婚を経験し、住まいについて深く悩みました。結果的に私は持ち家にそのまま住み続けるという選択をしましたが、その決断に至るまでには多くの検討と準備がありました。
この記事では、私の体験談を交えつつ、持ち家に住み続ける場合の注意点と、それ以外の選択肢についてもお伝えします。
私が持ち家に住み続けることを決めた理由
離婚後の住まい探しは、新しい生活の第一歩です。特に、子どもがいる場合、「どこに住むか」は慎重に考えたいですよね。
私自身、離婚を経験し、住まいについて深く悩みました。最終的に選んだのは、「持ち家にそのまま住み続ける」という選択でした。
ここでは、その決断に至った理由と、実際の手続きで直面したリアルな体験をお話しします。
なぜ持ち家に住み続けることにしたのか
持ち家に残ることを決めた理由は、主に以下の3つです。
- 子どもの生活環境を変えたくなかったから
転校や新しい友達づくりは、ただでさえ心に負担がかかる離婚後、子どもたちにとって大きなストレスになり得ます。住み慣れた家、学校、友達とのつながりを守ってあげたかった。子どもたちの生活の変化を最小限に抑えることを第一に考えました。 - 子どもを連れての引っ越しが大変だったから
ただでさえ手続きや話し合いで手一杯の中、子どもを連れての物件探しや引っ越しの準備は、想像しただけでも心が折れそうでした。
実際に物件探しもしましたが、子どもが3人いるので3LDK以上の広さが必要。将来の進学を考えて学区や駅からの距離も考慮すると、田舎でもそれなりの家賃がかかります。
さらに、持ち家の家具は賃貸には大きすぎて、買い替えが必要なものが多く、引っ越し費用+新しい家具・家電の購入費まで考えると、初期費用が莫大になることが分かりました。こうした金銭的な負担も大きな理由です。 - 元夫が「自分が出ていく」と決めてくれたから
離婚原因はほぼ元夫にあったため、私が家を出るという選択肢はありませんでした。元夫も、子どもたちの生活を考えて「自分が出ていった方がいい」と判断してくれました。
持ち家に住み続けるための手続きと注意点
持ち家に住み続けるためには、多くの手続きや話し合いが必要でした。
特に大変だったのがお金に関することです。離婚時に家を売却することも検討しましたが、家の売却額がローンの残高を下回る「オーバーローン」の状態だったため、売ってもローンが残ってしまうことが判明。残ったローン+賃貸の家賃を支払っていくのは現実的ではないと判断しました。
そこで、二人で話し合った結果、「今はどちらかが住み続け、今後の状況を見て売却する」という方向になりました。家の維持にかかる費用はすべて私が負担する代わりに、子どもたちのために私が家に残るという約束です。
特に大変だったのが固定資産税の支払いでした。一括で支払うのは難しく、分割手続きをすることに。ここで痛感したのは、「翌年分と重なって支払いが大変になる」ということでした。お金の管理は本当に重要だと身をもって知りました。
新生活が落ち着いてから検討したこと
生活が落ち着いた頃、「この大きな家を維持していくのは大変かもしれない」と思い、家を売却して県営住宅などに引っ越すことも考えました。
しかし、この決断は後悔することになるかもしれません。
「住まいの確保」は、その後の生活を大きく左右する重要な決断です。ぜひ、あなたの状況に合った最善の選択をしてください。
持ち家以外の住まいを探す場合の選択肢
「持ち家がない」「経済的に持ち家を維持するのが難しい」という場合、選択肢は大きく分けて賃貸物件・公営住宅・UR賃貸住宅があります。私自身も一度は検討したので、そのとき感じたことを交えながら紹介します。
賃貸物件
私も離婚を決めたとき、まず頭に浮かんだのが賃貸への引っ越しでした。
自分の収入に合わせて場所や広さを選べるのは大きなメリットですし、学区を変えない物件を選べば子どもたちの生活リズムも守れます。
ただ、実際に探してみると現実はなかなか厳しく…。敷金・礼金などの初期費用に加え、毎月の家賃がかかります。特に子どもが3人いる我が家の場合、3LDK以上が必須で、私が住んでいる田舎でもそれなりの金額になりました。さらに引っ越し費用や新しい家具・家電の買い替えまで考えると、負担が想像以上に大きいと感じました。
公営住宅
次に考えたのが公営住宅です。所得に応じて家賃が安く設定されるのは本当にありがたい仕組みで、シングルマザー・ファザーにとっては生活の助けになると思います。
ただ、公営住宅は入居条件が細かく決まっていて、申込みも抽選になることが多いです。私も調べてみましたが、タイミングによってはなかなか入れない可能性があると知り、現実的にすぐ住めるわけではないと感じました。
UR賃貸住宅
UR賃貸も調べました。礼金・更新料・仲介手数料・保証人が不要なのは魅力です。実際、保証人探しに悩む人にとってはとても助かる制度だと思います。
ただ、公営住宅に比べると家賃は高めの設定。魅力的だったのですが、私の場合は同じ学区に引っ越し先がなく、断念しました。
最後に
住まいは、新しい生活の基盤となるとても大切な場所です。
子どもの学校や保育園、通勤経路、そして何より「子どもが安心して暮らせる環境」を第一に考えることが大切だと、私自身強く感じました。
正直、私も離婚直後は「この家を維持できるのかな…」「賃貸にした方が気楽かもしれない」と何度も揺れました。実際に公営住宅や賃貸の情報を集めて、何度もシミュレーションをしました。
でも最終的には「子どもたちの生活環境を守りたい」という気持ちを優先し、持ち家に住み続ける選択をしました。もちろん、固定資産税やローンの支払いなど現実的な負担もあります。それでも今振り返ると、この選択が子どもたちの安心につながり、私自身も落ち着いた気持ちで新しい生活を始められたと感じています。
どの選択が正しいかは、人それぞれの状況によって違います。大切なのは「自分と子どもにとって何が一番安心できるか」をじっくり考えることだと思います。
あなたの新しい生活が、少しずつでも穏やかで安心できる日々になっていきますように。